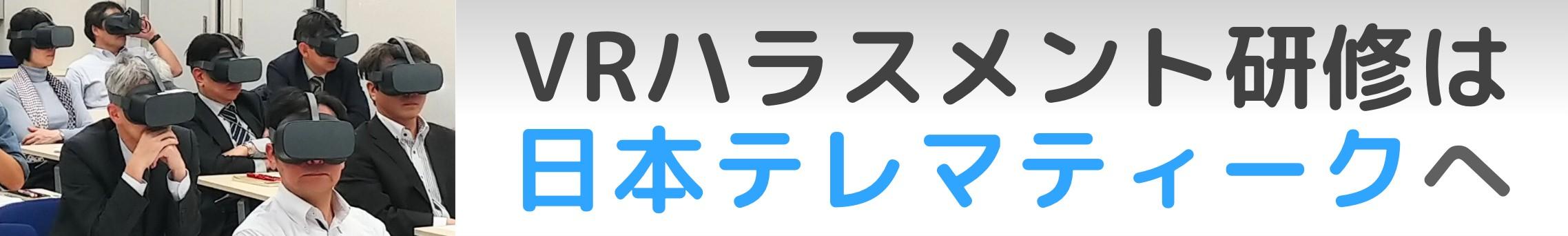人事・労務担当者が教える法的知識と実践ガイド_【Vol.2】

その「いじり」、大丈夫?グレーゾーン・ハラスメントの見極め方
皆様、こんにちは。 人事・労務担当のフクさんです。
毎日うだるような暑さが続きますが、夏バテしていませんかな?
お盆休みでリフレッシュできた方も多いでしょうな。休み明け、羽目を外しすぎて、会社での立場まで外さないように…なんて、失礼しました。
さて、第2回のテーマは、多くの方が判断に悩む「グレーゾーン・ハラスメント」です。白黒つけがたい職場のモヤモヤに、どう向き合えば良いのでしょうか。
これってハラスメント?職場のモヤモヤ
- 「熱心に指導したら、パワハラだと受け取られた」
- 「場を和ませるための『いじり』が、相手を傷つけていたらしい」
- 「先輩からのプライベートな質問に、どう答えたらいいか分からない」
このように、明確なルール違反とは言えないものの、「これってハラスメント?」と感じる瞬間はありませんか。
このような白黒つけがたい言動が、いわゆる「グレーゾーン・ハラスメント」です。多くの職場で、こうしたモヤモヤがコミュニケーションを阻害する原因になっています。
なぜ「グレーゾーン」は生まれてしまうのか
グレーゾーンが生まれる背景には、主に二つの要因があります。
📌一つは「価値観の多様化」です。
世代や育った環境が違えば、冗談の許容範囲や心地よい距離感も人それぞれです。自分の「当たり前」が、相手の「不快」になっている可能性を常に意識する必要があります。
📌もう一つは「コミュニケーション不足」です。
信頼関係が築けていない相手からの厳しい言葉や踏み込んだ質問は、たとえ悪気がなくても、威圧感や不快感として伝わりやすくなってしまいます。
指導かパワハラか、その境界線はどこに?
特に管理職にとって「指導」と「パワハラ」の線引きは悩ましい問題です。その境界線を見極める鍵は「業務の適正な範囲を超えているか」という視点です。
例えば、ミスをした部下に対し、改善点を具体的に、他の従業員がいない場所で冷静に伝えるのは「適正な指導」です。
しかし、大勢の前で「だから君はダメなんだ」と人格を否定したり、他の業務に支障が出るほど長時間叱責したりするのは、業務上の必要性も相当性も逸脱しており、パワハラと判断される可能性が極めて高くなります。
目的が正しくても、手段や伝え方が不適切であれば、それはハラスメントになり得るのです。
人事が教える!グレーゾーン対処法まとめ
グレーゾーン・ハラスメントにはどう向き合えば良いのでしょうか。立場別にポイントを整理しました。
✅1.【受ける側】一人で抱え込まず、客観視する
不快に感じた言動を具体的に記録し、信頼できる人に相談しましょう。可能であれば「私はこう感じます」と、自分の気持ちを主語にして伝える(アイメッセージ)も有効です。
✅2.【行う側】自分の「つもり」を疑う
日頃から相手に関心を持ち、信頼関係を築くことが大切です。良かれと思っての言動が、相手を追い詰めていないか、常に想像力を働かせましょう。
✅3.【組織として】判断基準を共有する
研修などを通じて、どのような言動がハラスメントに該当し得るのか、具体的な事例を共有し、組織全体で認識を揃えることが重要です。
想像力こそがグレーをなくす最大の武器
グレーゾーンの問題は、ルールだけで完全に解決することはできません。
私たち一人ひとりが
「この言動は、本当に相手のため、組織のためになっているだろうか?」
と自問自答する姿勢が不可欠です。相手の立場を思いやる想像力こそが、グレーをなくし、クリアで健全な職場を創る最大の武器となります。
次回は「もしもハラスメントが起きてしまったら?」というテーマで、具体的な対応プロセスを解説します。